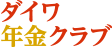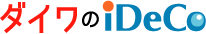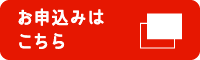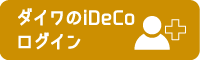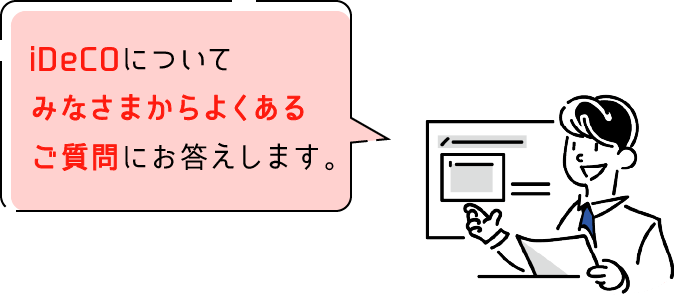
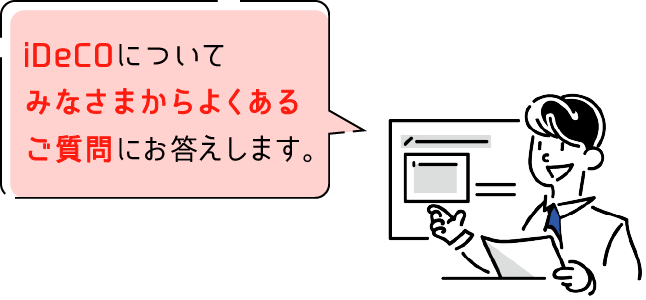
iDeCoってどんな制度?
- 確定拠出年金と公的年金の違いは何ですか?
-
公的年金とは主に国民年金と厚生年金保険のことです。
老後の生活資金の中核となるもので政府が運営しています。一方、確定拠出年金は企業や個人が主体の私的年金の一つで、公的年金を補完するものです。
個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の特徴は、
- (1)税制面で優遇されていること、
- (2)自己責任で運用すること、
- (3)原則60歳から受給(受取)できること、
- (4)受給方法・受給期間を選択できること
などです。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の商品性はどの金融機関も同じでしょうか?
-
iDeCoにおいて、各金融機関は運営管理業務を国民年金基金連合会から委託されています。
各運営管理機関ごとに、手数料や、運用商品のラインアップが異なります。
また、将来、選択可能な受給方法も異なります。 - 加入するとどんなメリットがありますか?
-
iDeCoは原則60歳から受給できます。
公的年金の受給は原則65歳からですので、60歳から65歳までのライフプランニングを考えることは非常に重要です。iDeCoは65歳までの期間の収入を補う手段としても注目されています。また、税制面で優遇されており、老後を見据えた資産形成の手段として最適と言えます。
- どのような税制メリットがありますか?
-
3つのメリットがあります。具体的には、
- (1)拠出時の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)、
- (2)運用時の運用益非課税、
- (3)受取時の税制優遇
の3つのメリットがあります。
- 収入がなくても節税メリットはありますか?
-
- (1)拠出時の所得控除
- (2)運用時の運用益非課税、
- (3)受取時の税制優遇
のうち、(1)所得控除のメリットはありません。ほか2つのメリットは享受できます。
- 拠出時の所得控除は配偶者の所得から控除できますか?
-
所得控除である小規模企業共済等掛金控除は他の社会保険料と異なり、加入者本人の所得からしか控除できません。
例えば、奥様がiDeCoに拠出した際にご主人の所得から控除することはできません。 - iDeCoで運用する資産を自由に引き出すことはできますか?
-
iDeCoは原則として、60歳まで運用する資産を引き出すことはできません。
通算加入者等期間が10年以上の方は60歳から受給できますが、10年未満の場合は、通算加入者等期間によって、受給できる年齢は異なります。
通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入者となった場合、加入者となった日から5年を経過した日より老齢給付金を請求することができます。
しかし、一定の要件を満たして脱退一時金の請求要件に該当する場合は、60歳未満であっても引き出すことができます。 - 給付(受取)はどのように受けるのですか?
-
給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
受取方法は、分割で受け取る「年金」、一括で受け取る「一時金」などから選択できます。
ただし、死亡の場合は遺族による一時金受取りのみとなります。 - 死亡したらどうなりますか?
-
ご遺族の方が請求をしていただければ、一時金として受け取ることができます。
死亡一時金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となりますが、他の相続財産とあわせて、法定相続人一人当たり500万円まで非課税枠があります。
なお、公的年金と同様、一定の障害状態になった場合は、障害給付金を受け取ることができます。 - 国民年金基金連合会はどんな組織ですか?
-
国民年金基金連合会は、iDeCoを所管する組織です。
大和証券などの金融機関は、iDeCoに関する業務を委託されています。
国民年金基金連合会のホームページは、こちら をご覧ください。
加入前の「よくあるご質問」
- 大和証券で取引をしたことがありません。
「ダイワのiDeCo」に加入することはできますか? -
大和証券での証券口座がなくても、「ダイワのiDeCo」に加入することができます。
企業型確定拠出年金も同様です。 - 現在、他社の口座でiDeCoを利用しています。
「ダイワのiDeCo」にも加入できますか? -
個人の方1人つき、複数のiDeCoを申し込むことはできません。
つまり、複数の運営管理機関(金融機関)のiDeCoに申し込むことはできません。なお、他の金融機関のiDeCoの残高を「ダイワのiDeCo」に移換(運営管理機関変更)することは可能です。
ただし、取り扱う金融商品が異なるため、他社で運用している資産はすべて解約され現金として移換されます。
そのため、手続きの際には現金で移換する資産について、「ダイワのiDeCo」の取扱商品から配分を指定していただく必要があります。 - iDeCoに加入するには何か条件がありますか?
-
65歳未満の方で、国民年金や厚生年金の保険料を支払っていることが条件となります。保険料の免除や猶予を受けている方は加入できません。また、企業型確定拠出年金に加入している方も加入できない場合があります。
- 加入者の種類や違いはなんですか?
-
国民年金の被保険者区分(第1号、第2号、第3号)やお勤め先の企業年金制度によって、掛金の上限額や加入手続きが異なります。
- 第1号被保険者とはなんですか?
-
ご自分で国民年金保険料を支払っている20歳以上60歳未満の方です。例えば自営業、フリーランス、学生、無職、第1号の配偶者、などが該当します。掛金の上限は年額81.6万円(月額6.8万円)です。
- 第2号被保険者とはなんですか?
-
70歳未満の会社員や公務員等、給与天引きで厚生年金保険料を支払っている方です。掛金の上限は、企業年金などに加入している方は年額24.0万円(月額2.0万円)で、企業年金などに加入していない方は年額27.6万円(月額2.3万円)です。
- 第3号被保険者とはなんですか?
-
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)の方です。掛金の上限は年額27.6万円(月額2.3万円)です。
- 医師ですが、第何号被保険者となりますか?
-
加入している公的年金が国民年金であれば第1号、厚生年金であれば第2号となります。一般的には開業医の場合には前者、病院等の勤務医であれば後者の可能性が高いと言えますが、まずは加入している制度をご確認ください。
- 主婦ですがパートをしています。第何号被保険者となりますか?
-
公的年金の保険料を給与天引きで支払っている場合は第2号(厚生年金に加入)、保険料を給与天引で支払っていない方は第3号(第2号の配偶者)になります。
- 以前の勤務先で企業型確定拠出年金を行っていました。
その後、手続きをしなかったため資産が特定運営管理機関に自動移換されてしまいました。
その資産を「ダイワのiDeCo」に移換することはできますか? -
可能です。こちらから移換のお手続きをお願いいたします。
- 掛金の金額は途中で変更できますか?
-
年1回可能です。従来は4月~3月の間に1回でしたが、平成30年分から前年12月~11月の間に1回になります。
- 掛金の拠出を一時的に止められますか?
-
加入者資格を喪失する手続きを取り、「運用指図者」になることで、掛金の拠出を一時的に停止することができます。
(但し、「運用指図者」となった期間については、退職所得控除を計算する際の勤続期間にカウントされませんので、可能な限り積立は続けた方が将来的にメリットがあります。) - 運用商品を途中で変更することはできますか?
-
運用商品の変更(売買)は、提示されている商品の範囲内で、基本的にお客さまの判断に基づいていつでも行うことが可能です。
(なお、「ダイワのiDeCo」では運用商品の変更を行う際、売買手数料はかかりません。) - 個人払込・毎月払いの場合で、銀行残高不足により引落不能となった場合はどうなりますか?
-
再引き落としはなく、その月は拠出がなかったものとなります。引落不能の通知等もございません。また、翌月に合わせて2ヶ月分引き落としすることもできませんのでご注意ください。なお、その月は加入期間からも除外されます。
申込のお手続きについて
- 申込書で基礎年金番号の記入を求められました。
基礎年金番号とはなんですか? -
基礎年金番号とは、公的年金に加入している被保険者全員に1人に1つ付与される番号のことです。
基礎年金番号は10桁の数字で表され、4桁と6桁の組み合わせとなっています。
iDeCoは、公的年金を補完する制度としてスタートしたため、基礎年金番号を付与されていることが加入資格の条件の一つとなります。 - 自分の基礎年金番号が分かりません。どうやって調べたらよいですか?
-
日本年金機構のページで紹介されています。詳しくはこちら をご覧ください。
- 掛金を引き落としで行いたいと思いますが、どの金融機関だと指定可能ですか?
-
掛金引落金融機関について(令和4年12月9日現在)
国民年金基金連合会と口座振替契約を締結し、iDeCoの掛金を引き落すことができる金融機関は以下の通りです。
- ■都市銀行、地方銀行、第二地方銀行
- ■信託銀行の一部(みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行)
- ■その他銀行(あおぞら銀行、イオン銀行、auじぶん銀行、GMOあおぞらネット銀行、埼玉りそな銀行、新生銀行、住信SBIネット銀行、ソニー銀行、pay pay銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行)
- ■信用金庫
- ■信用組合
- ■労働金庫
- ■信用農業協同組合連合会(信連)、農業協同組合(農協)
なお、以下の金融機関は国民年金基金連合会との口座振替契約がないため、掛金引落金融機関に指定することはできません。
- ■信託銀行の一部(野村信託銀行、SMBC信託銀行 など)
- ■ネット銀行の一部(セブン銀行 など)
- ■その他銀行
- ■外国銀行
- ■商工組合中央金庫
- ■農林中央金庫
- ■信用漁業協同組合連合会(信漁連)、漁業協同組合(漁協)
※ご不明な場合は、ダイワ年金クラブ・コールセンター(0120-396-401)までお問合せ下さい。
- 手続き関係書類の送付先はどこですか?
-
添付の返信用封筒を利用し、大和証券「ダイワのiDeCo」担当事務センターまでお送り下さい。
宛先
〒841-0026
佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1 フレスポ鳥栖2F
SBIベネフィット・システムズ株式会社
大和証券「ダイワのiDeCo」担当事務センター 行 - 加入申し込みをした後、掛金はいつから引き落しされますか?(資料請求の場合)
-
申込書の送付先であるSBIベネフィット・システムズで不備なく受付けられた日が、1日から14日の場合は翌月26日(休日の場合翌日)、15日から月末の場合は翌々月26日に2ヶ月分まとめて引き落しとなります。
- 年末調整に間に合わせるためには、加入手続きはいつまでに行えばよいですか?(資料請求の場合)
-
お勤め先で年末調整を行うためには、10月に払込証明書が発行されるため9月までの引落実績が必要になります。そのためには8月前半(14日)までに不備のない状態でSBIベネフィット・システムズに受付されている必要があります。9月までの引落実績が無い場合は、翌年1月下旬に郵送される払込証明書を利用して、確定申告で所得控除の手続きを行ってください。
申込書類の記入上の注意点について
- 加入申し込みに必要な書類は?
-
必ず必要となるのが、「個人型年金加入申出書(預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書、掛金運用配分設定申込書、を含む3枚つづり)」と「ダイワのiDeCoに関する確認書」および「本人確認書類」です。「事業主払込」を希望する第2号被保険者(会社員と公務員)の方は「事業主払込に関する証明書」も必要になります。
- 本人確認書類は何がありますか?
-
運転免許証やパスポート、保険証、個人番号カード、住民票があります。なお、個人番号カードのコピーは表面のみとし、裏面(マイナンバー)は絶対に送らないでください。また、住民票は取得から3ヶ月以内、コピー不可となります。
- 住民票の住所と居所が異なり郵便物は居所へ転送されるようにしていますが、加入申出書にはどちらの住所を書けばよいですか?
-
本人確認書類と同じ住所を記入してください。なお、加入後に記載された住所が変更となる場合は別途住所の変更手続きを書面で行っていただく必要があります。また、その際は新住所の本人確認書類が必要となります。
- 掛金額に下限はあるのですか?
-
「毎月定額」の場合は5,000円が下限となります。「納付月と金額を指定~」の場合は、年間の合計掛金で60,000円が下限となりますが、それ以外にもいくつかの制約があります。(詳細は「加入者月別掛金額登録・変更届」(「収入がなくても節税メリットはありますか?」ご参照)をご確認ください。)
- 掛金額を「納付月と金額を指定~」にしたいのですが、加入申出書に別紙と書かれている「加入者月別掛金額登録・変更届」はどこにあるのですか?
-
毎月定額で買付したほうが分散投資の効果を発揮できるという考えに基づいて、この帳票はスターターキットに同封しておりませんので、ご希望の方はダイワ年金クラブ・コールセンターまでご請求ください。
- 国民年金基金に加入している場合や、国民年金の付加保険料(月額400円)を支払っている場合は、掛金はどうなるのですか?
-
この場合、掛金の上限が月額68,000円からこれらの掛金(保険料)を引いて、1,000円単位に切り下げた金額となります。なお、下限の5,000円というのは変わりません。
- 「掛金運用配分設定申込書」で記入する運用商品は何本でも構わないのですか?
-
1本のみでも全ての商品を選択しても結構です。ただし、資産全体でご自分に適した資産配分となるように、商品の組合せを決めることが大切です。
- 「掛金運用配分設定申込書」は円単位での指定はできないのですか?
-
掛金の運用割合は1%単位での指定のみとなります。なお、加入後に積立てた資産を他の商品に預替える場合には、1円単位で指定することもできます。