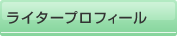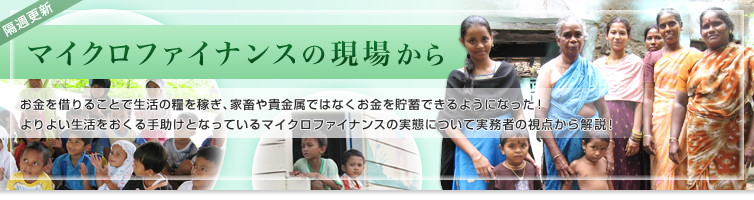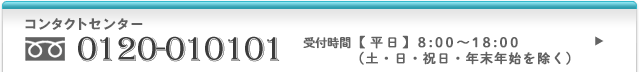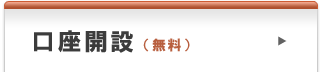今回は人口密度が低く、金融サービスを提供するには手間ひまもコストもかかる国が多いアフリカのマイクロファイナンス事業者の職員の現場での活動の一端をお伝えします。
きめ細かなサポートと低い人口密度
マイクロファイナンス事業者が定期的に顧客を訪問し、顧客の活動をモニタリングし、貯蓄を集め[1]、
貸付を行い、返済金を集めることはアフリカでも行われています。そこではお金と時間と人手をかけて適切なモニタリングをしないと、貸付金も返済されず、持
続的にマイクロファイナンス事業を経営していくために必要な利益を得ることができません。実際顧客の貯蓄の奨励などは行わず、政府や援助機関のお金を元手
に資金の貸付だけを行い、その後定期的に顧客を訪問・活動をモニタリングし、返済金を集めに回らなかった事業の貸付金の返済が低迷し、事業自体が続かずに
終わった事例もいろいろな国で聞きます。マイクロファイナンスという活動が人々の生活の一部となるには、マイクロファイナンス事業者によるきめ細かなサ
ポートが必要不可欠なのです。
ここで大きな課題となるのが人口密度です。アジアと異なりアフリカの多くの国の人口密度は低く、広大な土地のあちこちに集落が点在しています。例
えば2007年時点で、グラミン銀行で有名なバングラデシュの人口密度は1平方キロメートルあたり990人であるのに対して、アフリカ最大の人口密度であ
るモーリシャス(島国)は618人、タンザニアは42人、ケニアは64人、エチオピアは67人、セネガルは56人(2006)、モーリタニアに至っては3
人です(ちなみに日本は338人)(以上帝国書院)[2] 。このような土地でマイクロファイナンスを行うことは大変な労力を必要とします。
そのため、少しでも職員の労力を減らして金融サービス提供に必要なコストを削減し、より多くの地域に職員が行けるようにするために、第10回連載
で述べたような返済能力の見込める人々を選別(スクリーニング)するための顧客グループが形成されています。それに加えて、村長など村の居住者についてよ
く知る人物がグループに属する人物の居住証明をしたり、グループのメンバーが貸付を申請する際に「証人として」(保証人ではなく)署名したりするケースも
見られます。つまり村人の評判をよく知っている人物に「証人」となってもらうことにより、第一義的な顧客の審査が行われているのです。
[1] マイクロファイナンス事業者が貯蓄を集めることについては、マイクロファイナンス事業者の会員限で許可する国と、それも許可しない国があります(通常預金者保護の観点から、不特定多数の人から預金を集める業務は中央銀行管轄下の金融機関に限ります)。
[2] http://www.teikokushoin.co.jp/statistics/world/index03.html
マイクロファイナンス職員の活動例
ここでマイクロファイナンス職員の現場での活動の一端を紹介します。マイクロファイナンス職員は、顧客グループを週に1回、取引歴の長いグループ
の場合は2週間に1回などの頻度で定期的に訪問します。新規のグループの場合は1週間に3~4回など、訪問回数は顧客グループの状況によっても変わりま
す。一口に「訪問」と言っても、広大な土地に点在する村々のグループを1つ1つ訪問することは大変な仕事です。タンザニアのあるマイクロファイナンス事業
者の職員は、グループメンバーが借入金を使って行っている小規模なビジネスのモニタリング、返済の確認と督促、メンバー内の未返済がある場合は他のメン
バーによる返済の要請、トレーニングなどのために村を回っています。ちなみにタンザニアの農村部の小規模なビジネスには、靴磨き、魚加工、村落内の雑貨屋
(石けん、薬、燃料、小規模な農具などを扱う)、幹線道路沿いの飲食店、バイクタクシー(中国製のバイクの後ろに人を載せて運ぶ)、三輪車タクシー(数年
前からインドより輸入されるようになった大人3人が乗れる車)、自分で生産した野菜等の農作物を居住地から幹線道路まで運んで売る商売などがあります。都
市やその周辺部では道路を走る車の乗客に、食べ物、雑貨など多様な物を売るビジネスもあります。


このマイクロファイナンス事業者ではできるだけコストをかけずに顧客グループをまわるために、職員はバスなどの公共輸送手段を使って事務所からま
ずは村の近くの場所まで幹線道路を移動します。100km前後移動することもあるそうです(下記の写真奥左端のミニバスが公共の乗り合いバス。日本語が車
体に書かれたままの中古のミニバスもたくさん走っています)。そこからバイクや自転車を借りて幹線道路から離れた奥地のグループのある村まで行きます。何
の輸送手段もなければ炎天下を歩くわけですが、10km程度は徒歩圏だそうです。また、グループのミーティングが朝一番の時などは前夜からその村に行き、
電気も水道もないメンバーの家に泊めてもらうこともあるそうです。このような仕事は若くて体力のあるスタッフでないと務まらない、とある職員は話していま
した。

体力的な大変さに加えて、顧客とのコミュニケーション能力がとても重要となります。特に農村部の顧客の中には字が読めない者も多く、元本と金利を
定期的に返済すること、貸付条件、返済方法、メンバー相互による保証など、マイクロファイナンス事業者が提供するサービスを実施する上で必要不可欠なこと
について根気強く、忍耐強く説明する必要があります。せっかく説明しても、次回村に行ったときにはすっかり忘れられていて、最初から説明しなくてはいけな
いということもよくあるそうです。また、農村に行くと必ずしも貯蓄や貸付の話だけでなく、家庭問題を相談されたり、時には村の人のお葬式や結婚式などに参
加したりすることもあります。事務所でネクタイを締めてお客を待っていればよい仕事ではありません。
タンザニアの場合、マイクロファイナンス事業者への就職希望者は多く、非常に激しい競争を勝ち抜いて就職するそうです。職員には大学で会計や経
済、金融などを勉強した者も多いそうです。そのような職員が村に行く前には、提供するサービスについてだけでなく、字が読めない人とのコミュニケーション
の方法などについても十分に習ってから行きます。金融サービスを受けられない人にサービスを提供したいとの志を持って働き始めるのですが、中には上述した
ような日々の仕事を続けられず残念ながらやめていく人もいるそうです。あるマイクロファイナンス事業者では研修期間が終わった後、現場に出てから3~4ヶ
月でやめていく人もいるし、5年以内の退職者がほとんどであると話していました。
挑戦しがいのある活動
アフリカでマイクロファイナンスを行うことは実に挑戦しがいのある活動(challenging)である、と多くのマイクロファイナンス事業者が
話します。中には有志数人で始めた際に「絶対にうまく行かないよ」と何人もの人にやめるよう説得された、と話す人もいます。出身地が農村であり、貧困層、
特に女性がお金を借りられなくて苦労しているのを小さい頃から間近で見てきたので、そのような人々が少しでもお金を稼ぎ、生活をよくできればいいと思って
マイクロファイナンス事業者に就職したと話す、業歴9年(5年をとっくに超えています)のマイクロファイナンス事業者の支店長もいます。
マイクロファイナンスは上述したように手間ひまのかかる労働集約的な産業です。時間もコストもかかり「即収益」に結びつくわけではありません。諸
経費をカバーするために金利も高く設定せざるを得ません。タンザニアのあるマイクロファイナンス事業者は月利4%(期間は半年)であると話していました。
顧客の中には金利が高いという人ももちろんいます。しかし、一般的に農村部や遠隔地などに金融サービスを提供する事業者がいない中、定期的に訪問してくれ
るマイクロファイナンス事業者職員との信頼関係が築かれると、そう簡単にやめたり、他の事業者に移ったりはしないそうです。マイクロファイナンス事業者と
顧客との長期的な関係は、職員による日々の地道な活動に支えられています。
このように手間ひまのかかる活動はそう簡単には拡大できるものではありません。あるマイクロファイナンス事業者は、「確かに最初は時間も手間もか
かり難しい。しかし、一端事業が軌道に乗れば、時間をかけてサービスを使える顧客数を増やしていくことは可能だと思う」と話していました。マイクロファイ
ナンスを使って多くの人々が少しでも所得を得て貯蓄し、生活をよくするためには、マイクロファイナンス事業者職員による地道な日々の活動が必要不可欠なの
です。
(鳥海直子)