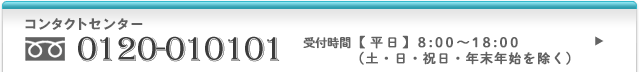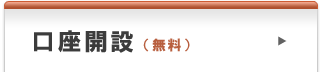|
|
|
資金使途 |
最大貸付額 |
期間 |
金利 |
担保 |
|
農業 |
300,000FCFA(通常は100,000~150,000FCFA) |
7ヶ月 |
年利18%(月割りで7ヶ月に計算) |
貸付額の20%相当をMFIに貯蓄、グループ保証 |
|
畜産 |
(i)肥育目的: 150,000 FCFA |
7ヶ月 |
上記と同じ |
貸付額の20%相当をMFIに貯蓄 |
|
(ii)飼育目的: 1,000,000 FCFA |
3年間 |
年利12% |
牛など購入家畜、冷蔵庫、車 | |
|
農業機械購入 |
3,200,000 FCFA |
4年間 |
年利12% |
購入機械 |
MFIの貸付の元手は、一般的にメンバーの貯蓄です。多くの場合、生活に必要な資金を頻繁に引き出すことの多いメンバーは1年超の貯蓄 を行えず、MFIにとって1年を超える中長期の資金を確保することは困難です。そのため、一般的にはMFIがメンバーの需要に応えて中長期の貸付を行うこ とは難しく、期間1年未満の短期貸付が中心となります。このMFIの場合も初めは自己資金を元手に貸付を行っておりました。しかし、貯蓄だけではメンバー の需要に見合う貸付を行うことが難しいことを認識し、外部からの資金調達について慎重に検討し始めました。現在、外国の支援基金から中長期資金を有償で借 り、メンバーに対する中長期貸付を行う元手としています。このように外国の支援を受けて農業機械購入や家畜飼育といった中長期資金の貸付も行い、人々の需 要に応えるMFIも出てきていますが、そのようなMFIはまだ非常に限られているのが現状です。
MFIのサービスを利用できない場合
MFIは増えているとはいえ、その数にも限りがあり、セネガルでもMFIのサービスを使える人々は残念ながらまだ限られています。このコラム第1回 の「途上国における高利貸業の実態」でも触れたように、セネガルにも様々な高利貸が存在しています。MFIのサービスを使えない人たちからは、以下のよう な資金繰りを行っているとの話が聞かれました。
・トレーダーから種子、肥料、農薬の購入資金を借りて購入し、収穫後に「籾」でトレーダーに返済する。借入時点で返済時の米の買付価格をトレーダー
により決められる。この方式では、あらかじめ決められたトレーダーによる買付価格が収穫時期の米の市場価格よりも低い場合、生産者(借手)には不利となり
ます。例えば80kgの籾の事前に決められた買付価格が7,000FCFAであった年の収穫時期の米の市場価格が10,500FCFA~
15,000FCFAだった事例もあるそうです。
・普段お金が必要になると、周辺の木を切って燃料として売ったり、家畜を売ったり、村によっては
役場にある金庫に「将来に備えて」ためておいた自己資金を使うそうです。人々は借入金返済後も手元に余剰があるときには(そのようなケースはあまり無いそ
うですが)、その余剰資金で家畜(雄牛、雌牛、ヤギ、羊など)を購入し、いざという時の備えとするそうです。ただ家畜の場合、必要な金額相当分だけを処分
することは難しいという別な問題も生じ、MFI等への貯蓄と比べると利便性が低い側面があります。
次回は途上国の人々の貯蓄について紹介する予定です。
(鳥海直子)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。
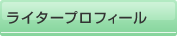
-
- 三井久明(みつい ひさあき)
- 専門分野はマイクロファイナンス、公共財政、民間部門振興、援助政策。 早稲田大学大学院経済学研究科修士課程およびUniversity of Sussex (IDS) Mphil課程修了。1990年に財団法人国際開発センターに入職し、現在は主任研究員。明治学院大学および早稲田大学にて非常勤講師を勤める。主に東南 アジア、南アジア地域において貧困削減、産業振興、国営部門改革にかかわる各種の調査研究に従事。
- 鳥海直子(とりうみ なおこ)
- 専門分野はマイクロファイナンス、農村金融、開発経済、農村開発。 世界銀行認定マイクロファイナンス・トレーナー。Institute of Social Studies 開発経済学修士課程修了。民間企業勤務、アジア経済研究所開発スクール、留学を経て、1994年に財団法人国際開発センターに入職し、現在は主任研究員。 市場経済移行諸国における農業開発、アフリカ農村地域の生計維持についての調査研究等、農業・農村開発分野を中心とした複数の調査研究に従事。
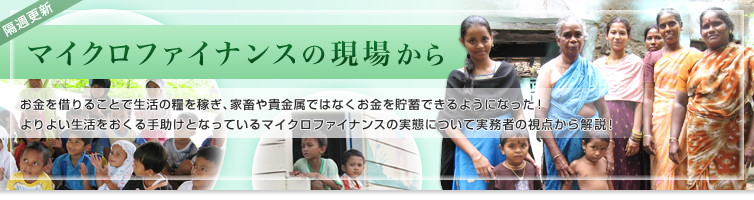
 セ
ネガルも日本と同じようにお米を食べる習慣があり、味つけしたご飯の上に魚や野菜などをのせたチェブジェンなど、おいしい料理がたくさんあります。米を生
産している北部地方では、農地を機械で耕作したり、種子や肥料、農薬などを買ったりするためにお金が必要です。政府系金融機関を通じた融資も行われていま
すが、複数の農家から構成されるグループが対象であり、個人向けの融資がありません。そのためグループ内に返済不履行農家がいると借りられません。また、
融資対象も米が中心で他の作物に使うことが難しいこと、貸付期間も播種から収穫までの1年未満の短期融資が中心であり、例えば機械を購入するために1年超
の中長期融資が必要となっても融資が受けられないといったこともあります。またこの政府系金融機関の融資総額にも限りがあり、希望してもすべての人が借り
られる訳ではありません。そのためいくつかのMFIは、農家の近くで貸付や貯蓄などの金融サービスを提供しています。この「農家の近くで」ということが借
り手にとってはとても大切です。なぜなら、銀行は大抵地方の主要都市にしか支店を置かず、人々がそこに行くにはバスやバイク等を乗り継ぎ、時間とお金をか
けて行く必要があるので、容易には行けない場合も多いからです。
セ
ネガルも日本と同じようにお米を食べる習慣があり、味つけしたご飯の上に魚や野菜などをのせたチェブジェンなど、おいしい料理がたくさんあります。米を生
産している北部地方では、農地を機械で耕作したり、種子や肥料、農薬などを買ったりするためにお金が必要です。政府系金融機関を通じた融資も行われていま
すが、複数の農家から構成されるグループが対象であり、個人向けの融資がありません。そのためグループ内に返済不履行農家がいると借りられません。また、
融資対象も米が中心で他の作物に使うことが難しいこと、貸付期間も播種から収穫までの1年未満の短期融資が中心であり、例えば機械を購入するために1年超
の中長期融資が必要となっても融資が受けられないといったこともあります。またこの政府系金融機関の融資総額にも限りがあり、希望してもすべての人が借り
られる訳ではありません。そのためいくつかのMFIは、農家の近くで貸付や貯蓄などの金融サービスを提供しています。この「農家の近くで」ということが借
り手にとってはとても大切です。なぜなら、銀行は大抵地方の主要都市にしか支店を置かず、人々がそこに行くにはバスやバイク等を乗り継ぎ、時間とお金をか
けて行く必要があるので、容易には行けない場合も多いからです。