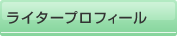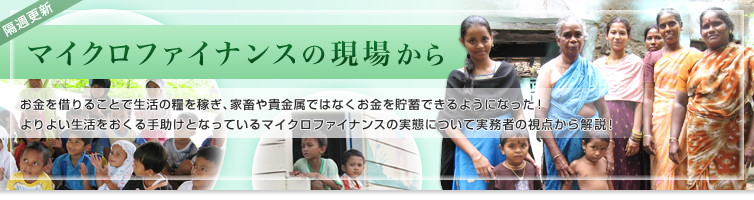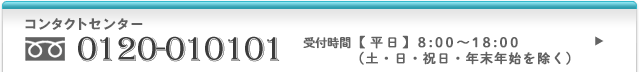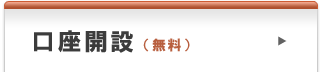そもそもお金のない人たちがなぜ金融サービスを必要とするのかと不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。今回は途上国の貧しい人々にとって、金融サービスを使えるとはどういう意味があるのかについて述べます。
様々な金融サービスへの需要
途上国の人々は様々な方法で生計を立てています。例えばアフリカでは農牧林水産業など第1次産業を主たる生活の糧とする人々が多いのですが、それだ
けで家族全員が1年間、1日3食食べることは難しい家庭も多く存在します。例えば農業の場合、自分で栽培した農作物を庭先に貯蔵して日々の糧にしたりしま
す。

何人かの農家が集って一緒に穀物を倉庫に貯蔵し、必要な時には相互に穀物の貸し借りを行う穀物銀行のようなケースも見られます。

人々は年間を通して食物を確保するべく様々な工夫をしていますが、収穫期から次の播種(種まき)の時期までは食べられるものの、播種から次の収穫期までの間には貯蔵しておいた農作物がだんだんと底をつき、特に収穫直前のやりくりがとても苦しいとの声もよく聞きます。
そのような時のために人々はできるときには少しでも貯蓄しておきたいと考えます。これまでの連載でも触れたように、近隣に銀行やマイクロファイナ
ンス機関などお金を安心して預けられる機関がなければ、農産物、ラクダ、牛、ヤギ、羊、鶏などの家畜、貴金属、あるいは缶の中にためるなどの形で貯蓄する
しかありません。しかし、穀物を貯蔵しても時間とともに品質も劣化しますし、ネズミなどに食べられることもあります。家畜の場合、旱魃などで死ぬと再度購
入して大きくするには3~4年かかりますし、盗まれることもあります。貴金属や自宅での現金の保管も同様です。それ故現金の形で預けることで必要な時に必
要なだけお金を引き出して食べ物を購入したり、子供の学校の費用や薬代、交通費などにあてたり不測の事態に備えたいという要望は強いのです。ちなみにアフ
リカでは多くの国で小学校から制服を来て通学する子供を多く見ますが、この制服代がばかにならず、制服が買えないから子供を学校に通わせられないと話して
いた母親もいました。また冠婚葬祭費用もばかになりません。マラウィのあるトウモロコシ生産者は母親のお葬式のために通常の年の10倍ものトウモロコシを
消費したと話していました。
他方、降雨量が少ないなど自然条件が厳しい国々では、第1次産業だけで生活することは非常に難しい場合が多いです。そのような国では、例えば家族
の誰かが都市や場合によっては他国で働く、あるいは農閑期などに出稼ぎに行き、残った家族はその送金で生活資金を補って暮らせている場合も見られます。
モーリタニアのサハラ砂漠にある年間平均降水量が100mm未満の地域に住む女性は、オアシスで野菜を栽培しつつそれだけでは食べていけないので、ヌアク
ショット(モーリタニアの首都)とフランス(モーリタニアの旧宗主国)で働く子供達からの送金も使って生活していると話していました。この送金について
も、銀行や郵便局などの窓口でお金を受け取れる人ばかりではありません。そもそも途上国で送金を扱う金融機関は限られており、居住地の近隣にたくさんある
とは言えません。また、あったとしても字が読めない、あるいは計算ができないといった人々にとって、金融機関の窓口に行くことは心理的にも大きな負担とな
るという話もよく聞きます。金融機関の方でも職員が窓口で顧客に対して横柄な、あるいは傲慢な態度をとらないように指導している、という話も複数の国で聞
きました。国によっては国際バスの運転手に頼んでお金を運んでもらい、バス停で待つ家族に仕送りを渡しているといった話も聞かれます。このような状況にお
いて、人々が便利で安全な送金サービスを使えるということは、生活する上でとても大きな意味を持ちます。
貯蓄や送金のサービスだけでなく、生計を立てるためのお金も必要です。農業で言えば種子や肥料、農薬などを必要な時期に必要なだけ購入するための
お金が必要となります。天候状況に左右されやすい農業の場合、播種時期が遅れることで生産量が大幅に減少することもままあります。種子や肥料、農薬などを
購入するための融資制度がある国でも、申請から実際の融資実施までの手続きに時間がかかり、必要な時期に必要な種子や肥料を買えなかったという声もよく聞
かれます。小さなお店を開いたり、石けんやジュースなどを作ったりする小規模ビジネスを行うにも最初の元手となるお金は必要です。
貧しいからこそいろいろな金融サービスが必要
貧しい人々は様々な手段でお金を貯め、お金が必要な時には貯蓄を使ったり、親戚、友人、知人、隣人等から短期間、無利子で借りたり、高利ではあるが
必要な資金をすぐに貸してくれる貸金業者から借りたり、マイクロファイナンス機関等から借りたり、多様な手段を使い分けてやりくりをしています。インド、
バングラデシュ、南アフリカの3カ国の貧困家庭の家計調査をした本
によると、貧困家庭であるほど少額のお金を出し入れする機会が多く、生計を維持する上でその管理がとても重要となっています。この家計調査では、友人・親
戚・隣人等から借りる場合、比較的融通は聞きやすい反面、知っている人から借りることへの抵抗もあるので、わざわざ離れた地域に住む知人に借りるといった
話も報告されています。また融通性は知人等からの借り入れに劣るものの、より信頼できるのはマイクロファイナンス機関であると認識しているケースも報告さ
れています。このように貧しいから金融サービスが不要なのではなく、貧しいからこそ、いろいろな方法を駆使して日々のやりくりをする必要があり、いろいろ
な金融サービスを必要な時に必要なだけ使えることは重要な意味を持つのです。
かつてはマイクロクレジットと呼ばれ、小額資金の貸付だけを行う機関も多かったのですが、上述したように人々の需要に応える形で貸付だけではな
く、貯蓄や送金等多様な金融サービスを提供するマイクロファイナンス機関が増えてきています。このようなマイクロファイナンス機関のサービスを受けられる
人々はまだまだ限られていますが、2006年にノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行のモハメド・ユヌス博士が「金融サービスを受けることは人権の一つ」
と明言したように、貧しい人々が生計を維持・向上させる上で、金融サービスは医療や教育と並ぶ基礎的なサービスであるという認識が徐々に広まりつつありま
す。
(鳥海直子)