 ライフプランコラム「いま、できる、こと」vol.360(2025年8月22日)年金についてのお話
ライフプランコラム「いま、できる、こと」vol.360(2025年8月22日)年金についてのお話
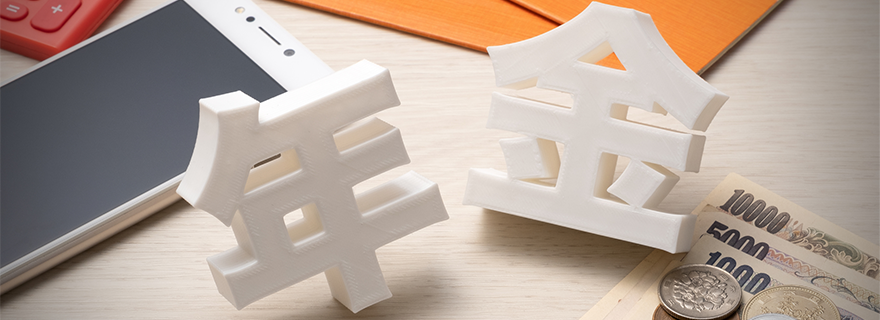
前回はiDeCo(個人型確定拠出年金)についてご説明させていただきました。今回は、年金全般のお話をさせていただければと思います。
日本の公的年金制度は、①20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金と、②会社員や公務員などが加入する厚生年金保険があります。
また、年金を受け取る制度にも色々あります。国民年金から支給される年金は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」と呼び、厚生年金保険から支給される年金は「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」と呼びます。複雑に感じる年金制度ですが、焦らずに一つひとつ用語と意味を確認していくことにより、理解を深めることができます。
公的年金は原則、終身(亡くなるまで)受給できますが、公的年金がなぜ一生涯の保障をすることができるのか疑問に思ったことはないでしょうか?その答えは、年金制度が積立方式ではなく、賦課方式を基本としているからです。賦課方式とは、年金支給に必要なお金を、その時代の働く世代が納めた保険料から用意するしくみです。働く世代から年金受給世代への仕送りをイメージとすると分かりやすいです。このしくみによって、公的年金は終身(亡くなるまで)受給できるようになっています。
公的年金は国の社会保障制度の一つです。国民一人ひとりが社会保障の担い手であるという意識を持ち、暮らしていくことが大切です。
それでは、皆さんは、ご自身の年金がどうなっているのか把握されていますでしょうか?
先ず、「いつから」「いくら」受け取れるかご存じですか?
受け取り開始時期は60歳から75歳までの間で選ぶことができます。受け取る期間を遅らせれば年金額が増える一方、早めに受け取ると減ります。尚、受け取る年金額は、保険料を納めた時期などにより、一人ひとり違います。毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」にて、記録に「もれ」や「誤り」がないかチェックし、将来の年金額に関する情報も確認しましょう。
また、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額の試算を行うことができます。ご自身のスマートフォンやパソコンから確認し、老後の生活設計について考えていきましょう。
できるだけ長く働くなどしっかり保険料を納めること、年金を受け取る時期を遅らせること、60歳を過ぎても加入する私的年金と組み合わせること、などの選択肢により毎月の受け取る年金の額を増やすことができます。現代社会は、昔よりも健康で長生きできるようになっています。老後の過ごし方を考えて計画的に行動していきましょう。
- 出所:厚生労働省HP
人気のキーワードでコラムを探す
商号等:大和証券株式会社 金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第108号
確定拠出年金運営管理機関登録票 確定拠出年金運営管理業
登録番号769 大和証券株式会社
©Daiwa Securities Co.Ltd.

