不公正取引行為の禁止について
「相場操縦的行為として疑われる可能性のある取引類型」
1約定させる意思のない大量の注文発注・取消し(見せ玉・見る玉)
- ・大量(または複数)の注文を発注し、その後に取消す。
- ・売付(または買付)後に、大量(または複数)の未約定の買い(または売り)注文を取消す。
具体例
投資家Hさんは保有する□●株を1000円で売りたいと思っていますが、株価は一向に上がりません。そこで、Hさんは1000円での売り注文を発注した後、970円で20万株、965円で20万株の買い注文を発注しました。その後、この買い注文を見た他の投資家から買い注文が入りはじめ、Hさんの1000円の売り注文が約定されました。Hさんは売り注文が約定されたので、970円および965円の買い注文を取消しました。
| 見せ玉がない場合 | 見せ玉発注後 |
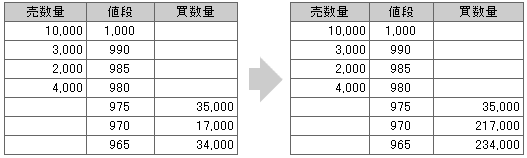
ポイント
Hさんは、保有株を売却するために、買う意思のない大量の注文を発注し、株価が下がりにくい状況であると他人に誤解を与え株価を上昇させる目的で行ったものと推測されることから、「見せ玉」とよばれる違法行為に該当する可能性が高い取引と考えられます。注文の取消しを行うことが全て違法行為となるわけではありませんが、大量の注文発注・取消しには注意が必要です。
同様に、買い板(売り板)の状況を見るために約定する意思のない大量の注文を発注し、取消すことも、「見る玉」と呼ばれる違法行為に該当する可能性があります。
2市場関与率が高くなっている
- ・出来高の少ない銘柄で売り注文(または買い注文)のほとんどを買付ける(または売付ける)取引を反復する。
- ・直近の出来高に比べて大量の注文を発注し、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
- ・立会終了間際(大引け間際)に大量の注文を発注する。
具体例
投資家Aさんは、〇×株が小型株で、日々の出来高も少ない銘柄であることから、自分である程度〇×株を買付ければ、株価が上昇してうまく売り抜けることができるのではないかと考えました。そこでAさんは、日々の板状況を見ながら、売り注文が出たところをすかさず買付けていきました。すると、〇×株は上昇し、出来高も増え始めることとなりましたが、この間、Aさんの取引は連日、出来高の50%~70%を占めていました。その後、〇×株の値動きや出来高の増加を知った他の投資家が追随したことにより、〇×株の株価はさらに上昇し、出来高も増加したため、Aさんは買付けた株を全て売却し、利益を得ることができました。
ポイント
特定の投資家の市場関与率が高いことだけをもって、直ちに法令違反になるわけではありませんが、継続的に市場関与率が高い場合には、株価形成に与える影響が必然的に高くなっていると考えられます。
このケースでAさんは、自分の保有株を売り抜けるために、他の投資家に誤解を与えることを目的として、売り注文をすかさず買付けるような売買を行った結果、市場関与率が高くなっていますが、このような行為は「相場操縦的行為」と呼ばれる違法行為に該当する可能性の高い取引と考えられます。市場関与率が継続して高くなるような場合には注意が必要です。
3買い上がる(または売り崩す)注文
- ・短時間に株価が急騰(または急落)している銘柄について、買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
- ・直近の出来高に比べて大量の注文を発注して、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
- ・一日のうちで(または複数日に渡って)反復継続して買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
具体例
投資家Bさんは保有する〇△株を、高く売りたいと考えています。しかし〇△株は1日の出来高も少なく、株価もなかなか上がってきません。そこでBさんは自分で○△株の株価を上げれば、他の投資家の買い注文が入りうまく売り抜けられるのではないかと考え、〇△株を540円から590円まで、1000株づつしか売り注文がない板状況を見て、590円で6000株の買い注文を出し、売り注文すべてを買付けました。さらにBさんは、その後の板状況から580円から600円まで3000株しか売り注文がないのを見て、600円まで買付けました。それを見た他の投資家から買い注文が入りはじめ、株価は上昇しBさんは〇△株を高いところで売却することができました。
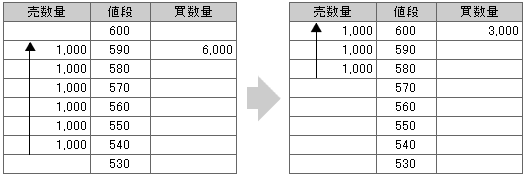
ポイント
上値で買付けることがすべて違法行為となるわけではありませんが、買い上がるような注文が反復継続される場合は、Bさんのように、保有株を売り抜けるために、他の投資家の注文を誘い込むことを目的として、自分で株価を上昇させたのではないかとの疑念を持たれる可能性が高いことから、このような注文には注意が必要です。
4高値(または安値)を付ける注文
- ・当日の高値(または安値)を付ける取引を反復する。
- ・高値(または安値)形成後すかさず追随する取引を行う。
- ・複数日に渡って反復継続した高値(または安値)を付ける取引を行う。
具体例
投資家Cさんは信用取引により△×株を買建てていますが、思うように株価が上がらず、今の株価水準で決済すると損失が出てしまいます。Cさんはなんとか株価を上げようと考え、△×株を自分で継続的にその日の高値を付ける買付を繰り返し行いました。その後、株価は値上りし、他の投資家の買い注文も増え出来高も増加した結果、Cさんは利益が出る水準で決済することができました。
ポイント
その日の高値で買付けることがすべて違法行為となるわけではありませんが、継続的な高値形成が行われる場合は、Cさんのように、他の投資家からの注文を誘い込む目的で意図的に株価を上昇させたのではないかとの疑念が持たれる可能性があります。このような、継続的に高値を形成する注文には注意が必要です。
5株価を固定させるような注文
- ・市場の売り(または買い)数量に合わせた買い(または売り)数量の注文を発注する。
- ・出来高の少ない銘柄で売り注文のほとんどを買付ける取引を反復する。
- ・株価の下支え(または頭押さえ)の効果を持つ大量の注文を発注する。
- ・一日において(または複数日に渡って)株価を下支える(または頭を押さえる)ような反復継続した注文を発注する。
- ・下値(または上値)の大口指値注文の一部を順次高く(または低く)変更する。
具体例
投資家Dさんは信用取引で×□株を買建てていますが、信用取引の委託保証金としても同じ×□株を代用有価証券として差入れており、いわゆる「二階建取引」を行っています。
ところが、株式相場が下落基調となり、×□株の株価が下がってきたため、これ以上×□株が下がってしまうと追証が発生してしまうかもしれません。そこでDさんは追証の発生を回避するために、×□株を買い支えようと考え、×□株の売り注文が出ると買付けるという取引を繰り返し行いました。その結果、×□株式は下げ止まり、Dさんは追証の差入れを回避することができました。
ポイント
公募増資などにおいては、「安定操作取引」といって一定の要件の下、株価を買い支えることが認められていますが、それ以外の場合でDさんのように、株価の値下がりを防ぐために、株価を一定の価格で固定させるような取引は、違法行為に該当する可能性の高い取引と考えられます。このような、株価をくぎ付け・固定させる注文には注意が必要です。
6立会終了間際の注文(終値関与)
- ・立会終了時を含む特定の時間帯において大量の注文を発注する。
- ・当日の(または複数日に渡っての)立会終了時を含む特定の時間帯において反復継続した注文を発注する。
- ・複数日に渡って反復継続した引け成り注文を発注する。
具体例
投資家Eさんは●×株を保有していますが、現在の株価は買付価格を下回っています。Eさんは何とか株価が上がらないものかと思い、後場の立会終了間際や大引けで、直前の価格よりも終値を高くするような買い注文を数日間継続して発注しました。その結果、●×株は上昇し、Eさんは保有株を売却して利益を得ることができました。
ポイント
立会終了間際や大引けでの買付(または売付)自体が違法行為となるわけではありませんが、株価の終値は新聞紙面に掲載され相場の強弱を見る上で参考とされる値段であり、Eさんのように、保有株を売り抜けるために、意図的に終値を高くする行為は、「相場操縦的行為」と呼ばれる違法行為に該当する可能性の高い取引と考えられます。このような、継続的に終値に関与する注文形態には注意が必要です。
7仮装・馴合い売買
<仮装売買>
- ・ご自身の売り注文と買い注文が対当する売買を行う。(クロス取引)
具体例
■ザラ場のクロス取引
投資家Fさんは、現値が996円のところ、売り注文と買い注文(1000円に700株)を自ら発注して1000円で約定させることで、株価の引上げを行いました。
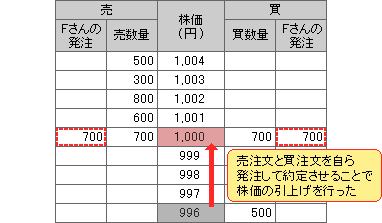
■売り買い不均衡なクロス取引
投資家Fさんは、寄付前に気配が996円のところ、成行売り注文1000株と成行買い注文2000株(実質的に差引き1000株の買付)を自ら発注して、寄付で約定させることで、寄付の株価の引上げを行いました。
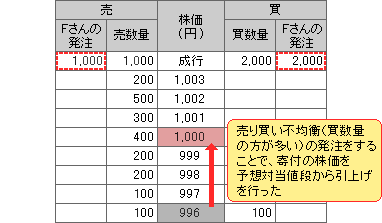
ポイント
Fさんの行った売買は権利の移転を目的としない取引であり、取引が活発に行われていると他人に誤解を与え、市場の価格形成にも影響を及ぼしていることから、「相場操縦的行為」と呼ばれる違法行為に該当する可能性の高い取引と考えられます。このような、売買には十分な注意が必要です。
<馴合い売買>
- ・特定の顧客との間で対当する売買を行う。
具体例
投資家Fさんは□△株を買付けましたが、出来高の少ない株で、株価もなかなか上がってきません。そこで、Fさんは、□△株の取引が活発化したように見せかけようと自分の売注文を自分で買付けて値段を付けることを繰り返しました。さらに、Fさんは友人のGさんに相談し、Fさんの売り注文をGさんに買付けてもらうことにし、さらに、Gさんの売り注文をFさんが買付けることで株価を上昇させました。その後、□△株に他の投資家からの注文が入りはじめ、出来高も増え株価も上昇し、FさんもGさんも□△株を高値で売却することができました。
ポイント
FさんとGさんの売買は、あらかじめ通謀して行った取引であり、いずれの売買も取引が活発に行われていると他人に誤解を与える目的で行ったものであることから、「相場操縦的行為」と呼ばれる違法行為に該当する可能性の高い取引と考えられます。このような、売買には十分な注意が必要です。
 メニューを
メニューを